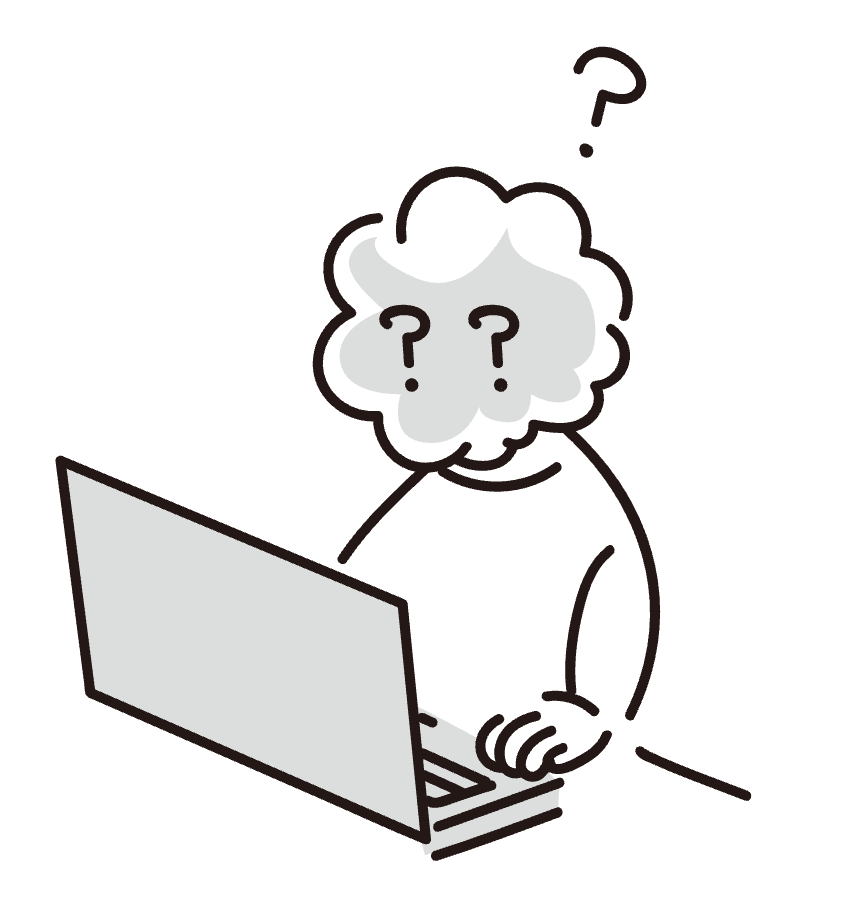
ブログが長続きするコツがあったら知りたい。
「ネタがない」は勘違いです。足りないのは材料ではなく、設計と分解の型です。
先に「誰に/何を/どう伝えるか」を決めてから、日常・経験・一次情報・検索情報を明示的にフレーミングすると、同じ素材でも無限に展開できます。
本記事では、ネタ切れの正体を整理し、今日から回せる「アイデア補給の習慣」を提示します。
「ネタ切れ」は設計不備から起こります

材料は日常に十分あります。
止まるのは、切り口を決める前に書き始めるからです。
まず「誰に/何を/どう伝えるか」を先に固定します。
対象読者、ゴール、伝達手段(記事タイプ・図解・事例)を決めると、同じ素材でも別物の価値に変わります。
書けなくなる根本原因=「軸」の曖昧さ
ターゲットが曖昧だと語彙がぶれて、誰にも刺さらない文章になります。
「この人の現状に、今必要な答えを届ける」と決めてから言葉を選ぶと、同じ事実でも届き方が変わります。
価格・機能の羅列ではなく、「どんな場面でどう役立ち、どんな感情になるか」まで描くと、読了率が伸びやすくなります。
雑記か特化かは「順番」で決めます
どちらにも利点があります。
雑記は続けやすく、特化は期待が揃います。
収益化が目的でも、ゼロから特化に張るより、雑記で執筆筋力と反応データを取り、ヒット領域を特化の核に寄せる流れが安定します。
ジャンル選定のコツ|好き×需要×立場
流行や単価だけで決めると挫折しやすくなります。
好き(続けられる)×需要(検索・課題の存在)×立場(語り手のポジション)で選びます。
体験者として語るのか、研究者として比較するのか、失敗からの学び手として検証するのかで、切り口が大きく増えます。
ネタの作り方:5分割フレームで量産します

探すのではなく、同じテーマを切り分けるほうが速くなります。
Why(理由)/What(定義・比較)/How(手順)/Mistake(失敗)/Case(事例)に分けて、読者の段階に合わせて並べ替えます。
この5本を1クラスターにして内部リンクで結ぶと、網羅性が高まり、継続的にネタが派生します。
ジャンルが決まらないときの入口

棚卸し→小さく公開→反応で寄せるが安全です。
経験・知識の棚卸しで1本、生活の質が上がる小ネタで1本、短文雑記で1本の三方向から着手します。
PVや滞在時間、検索クエリの質で重心を見極めます。
「1秒でわかる」見出しと導入を作ります
読者は最初の一瞥で読むか離脱するかを決めます。
見出しは読者の得を具体化し、導入は何を得て、今何をすべきかを二文で伝えます。
行間・改行・ひらがな比率・太字位置まで含めて視認性の編集を行うと、読み続けてもらいやすくなります。
避けたい悪手👇
① 難語で賢さを演出する→ 伝わらないので避けましょう。
② 前置きで結論を遅らせる→ 冒頭で結論を示しましょう。
③ 主語と述語をねじらせる→ 一文一義で整えましょう。
それでも書けない時の対処法

読者のタイプに合わせて対応を変えると効果的です。
「すぐに行動したい人」には、記事の最後に【今日やるべき一つの行動】を提示します。
「やり方がわからない人」には、冒頭で「まずA、次にB、最後にC」と手順をはっきり示します。
どうしても書けないときは、いったんブログから離れてインプットを増やすのも有効ですよ。
まとめ:悩む前に「設計→分解→明示」を回しましょう

ネタ切れはアイデア不足ではなく設計の不備から起こります。
最初に軸を定め、読者の状況に合わせて言葉を選び、Why/What/How/Mistake/Caseで分解します。
見出しと導入で「1秒で得がわかる」形に整え、前提・向き不向き・コストを明示します。
数をこなしながらこの型を磨けば、同じ素材からでも角度の違う記事を安定して生み出せます。
今回はここまでです。
ありがとうございました!

